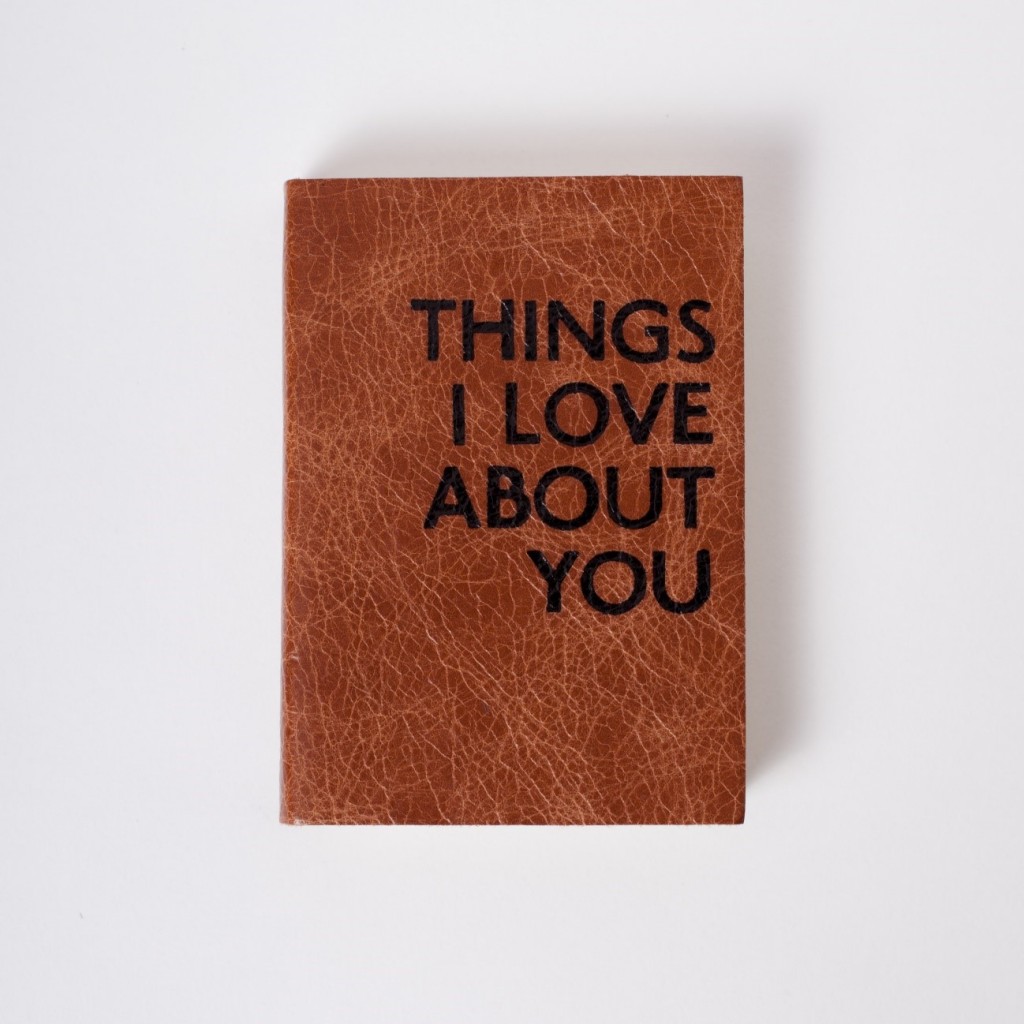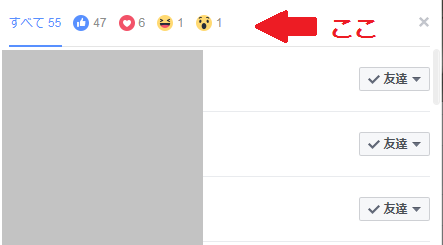LINEをよく使う方なら、メッセージと一緒にスタンプを送信する方も多いと思います。
絵文字より大きくて感情やリアクションを伝えやすいのでとても便利ですよね。
しかし、返信は来たけれど文章は無くスタンプのみだった!そんなことがあった方もいるのではないかと思います。
スタンプしか送ってくれなかった相手の心理から、「本当に会話を終わらせたいのか」を考えてみました。
スタンプのみに対してどうしたらいいの?
どうやら、返信がスタンプのみだったことに対し「私はどうしたらいいの?」と少し考えてしまう方が多いようなのです。
質問系サイトには、そんなお悩みが多く見られました。
好きな人や友達とLINEしている時って楽しいですよね。出来れば長い期間、共通の話題や今日の出来事を話していたいと考える方も多いと思います。
しかし、決して大事な連絡事項のやり取りでは無かった為に、相手の本音が読み取れないスタンプに困ってしまい「私との会話を終わらせたいのかな」と不安に感じてしまう方もいるのです。
また質問系サイトでは、スタンプのみで終わってしまったやり取りに、どうしたら会話が続いたのだろうかと方法を考えているという方もいることが分かりました。
確かに、スタンプだけが返ってきても困ってしまいますよね。そのままにしておいても良いものか・・・どうしたらいいの? 逆に自分がそっけないとは思われたくないと悩みは更に深くなってしまいます。
スタンプのみの返信、その心理とは?
このように、学生同士のやりとりや付き合って間もない恋人のそっけない返信だけでなく時には親しい友人間や夫婦間でも頭を抱えてしまっているといった内容も幅広く、LINEは今や欠かせないコミュニケーションの場であることが分かってきました。
それでは、どうして返信がスタンプのみになってしまうのか。その最も多い理由から順番に、解決策も一緒に考えていきましょう。
最も多い理由!既読スルーは出来ないから
「返信をするのは面倒だけど、既読スルーをする相手ではない」そう感じたときにスタンプのみの返信をする方が多いようです。
面倒だとは感じていながらも、あなたからのLINEは嬉しいと感じていると思います。
マメな性格の人ばかりじゃありません。それくらいの手抜きは許してあげてもいいかもしれませんよ。
中には、「文字を打つよりスタンプを送ったほうが早いから」という理由で、忙しい時や手が離せない時に返信をスタンプのみで終わらせてしまう方もいるようです。
その場合はこちらも空気を読んで、とりあえず一旦会話を終わらせてあげたほうが相手への負担は少なくて済みます。
「また今度ね!」や「おやすみ」そんな一言を返信してあげることで、スタンプだけで終わらせてしまった相手の罪悪感も少なくなります。
そして会話の続きもしやすくなりますから、「会話が切れないと思わせない」のは関係を良好に保つコツかもしれませんよ。

実は困っているサインだった?
スタンプのみの返信がきてしまった時は、それまで自分がどんなメッセージを送っていたのか振り返ってみましょう。
他人への悪口や、ややこしい話など、返信する相手を困らせる内容を送ってしまっていることもあると思います。
もちろん時間に余裕があればいくらでも話は聞いてあげたいものですが、LINEに時間を縛られていることを良く思わない方もいるのではないでしょうか。
相手の反応に不満を抱いてしまうよりも、スタンプで反応を示してくれた気遣いにまずは感謝してみてはいかがでしょうか?
よく見ると可愛い顔のスタンプだったりして、その相手の印象が良い方向に変わることもあると思いますよ。
大喜利が始まっていた!?
種類が豊富なスタンプの中には「これっていつ使うの?」といった珍しいものも多いですよね。
ここぞという時に披露する為に、面白いスタンプを集めている方もいるほどのようです。
会話の内容に基づいたスタンプや、ギャグのようなものもあり、思わず吹き出してしまうものもあります。
最近はスタンプが飛び出てきたり、喋ったり歌ったりとバリエーションに富んできましたよね。
スタンプ好きの方は、文章で返信をするのはもちろんですが、自分で集めたスタンプをあなたに送ってみることで、一日の終わりに大喜利風にして笑ってほしかったのかもしれません。
スタンプのみの返信で会話は終わったけれど、なんだか変で面白いスタンプだった時は「面白い!山田くん、座布団一枚!」と返信してあげると喜んでもらえるかもしれませんよ。
ラブラブスタンプには注意が必要
メッセージ文にハートの絵文字があることで、自分に好意があるのでは?と思う男性が多いとよく聞きますよね。
絵文字と同じように、感情を大きくして相手に送れる為にスタンプを多用する女性は多くいるようです。
無料のものでも、必ずと言って良いほど「ハート」や「ラブラブ」を表す絵のスタンプがありますよね。
LINEの返信はスタンプのみだったけれど、ハートの絵の可愛いスタンプだったなという男性もいると思います。
一日の終わりに好きな女性からハートのスタンプが来るなんて、嬉しい事この上ないですね。
もちろんこれには男性に対する好意も含まれていると思います。
しかし、絵文字の場合と同様に無意識に(または計算で)男性の純心な好意を少々振り回してしまう可能性もあると思います。
本当の意味を知りたいのであれば、いずれは女性に真意を確かめる時が必要かもしれません。

また、逆のパターンもご用心です!
こちらは返信ではなく「男性から文章は無くスタンプだけきたけど、どういう意味?」という質問を見かけました。
どうやらこの女性は、突然スタンプだけが送られてきて困惑しているということのようです。
もちろん例外はありますが、何の文章も無くさほど意味の無いスタンプを送るだけだったならば、それこそ「大した意味など無い」と思ったほうが良いと思います。
よくモテる男性や、あなたと遊びたいと思っている場合、「何らかの反応があればデートにでも誘ってみようかな」と考えているのが大半のパターンだと思います。
あくまで女性の反応がありきの話のようで、自分からは行動しない作戦とも思われます。
では、本気度を見抜くポイントはあるのか? ちゃんとありますよ。
真剣に好意を寄せている女性ならば、きちんと文章でデートに誘いますよね。
あなたからの反応を待っているだけなんて、ちょっと寂し過ぎると思いますよ・・・
スタンプのみでも会話は続く?
誰しも一度は挑戦したことがあるのではないでしょうか?
スタンプを新たに集めなくても、もともと入っているスタンプだけでLINEをしている方もいますよね。
喜怒哀楽だけでなく様々なシーンを切り取ったスタンプが用意されています。
つい会話が盛り上がってしまい、スタンプ合戦になった!そんな経験あるのではないでしょうか。
例として(遅刻してしまうと連絡した場合)「ごめんね!」→「怒る」→「泣く」→「ドンマイ!」→「ありがとう!」→「どういたしまして」
こんな会話をスタンプのみで成立させてしまえると、ちょっと間抜けで笑えますし、相手との笑いのツボが合うことで距離感もグッと近付くような気がしますよね。
しかし、連絡事項がある場合はきちんと言葉で伝えてくださいね。
スタンプの解釈が違ってしまった為に険悪にならないように注意してください。

会話を終わらせたいわけではない!
少々例外的なケースも紹介してきましたが、スタンプのみの返信には様々な事情があると分かってきました。
手軽に送れるスタンプだからこそ、使い方は千差万別だったのですね。
「相手がそっけなくなってしまった」と肩を落としてしまう前に、返信が途絶えた理由や、連絡を取っているタイミングなど考えてみると良いかもしれません。
会話をしている感覚とは言え、こちらにもあちらにも都合はあるものです。
スタンプのみの返信がきてもしつこく後追いはせず、その日は終わらせておくというのが無難かもしれませんね。
会話は何度だって始められますから、今度はどんな話題で盛り上がろうかな?と楽しみに待っておく時間も必要なのかもしれませんよ!
【関連記事】
彼氏からLINEが返ってこなくて不安!返信せずに未読無視する男性心理とは
こちらの記事では、彼氏からLINEが返ってこなくて不安なときに読んでもらいたい記事です。
スタンプだけしか返ってこない、そもそも返信がない・・・
LINE(以前はメールだったわけですが)に関する悩みなんて…と感じるかもしれませんが、恋人間の大切なコミュニケーション手段です。
是非、パートナーの方と話し合って、上手く折り合いをつけてくださいね!